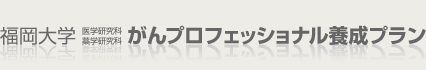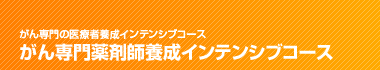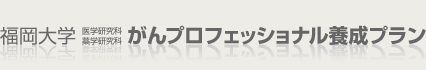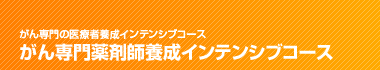|
カリキュラム
|
| 本インテンシブコースのカリキュラムでは、日本医療薬学会がん専門薬剤師養成研修コアカリキュラムに従い講義研修やがん専門薬剤師に必要な臨床経験(調剤、薬剤管理指導、緩和ケア)を通じて、がん専門薬剤師の職務に必要な高度の薬学知識・臨床知識・専門的技術を修得する。その中で、がん患者年10症例以上の自ら関与した臨床経験を積むとともに、がん専門薬剤師として相応しい態度を身につける。 |
| 1.講義研修 |
- 日本病院薬剤師会が主催する2日間の集中教育講義を受講すること
- NPO法人 臨床血液・腫瘍研究会のオンコロジーセミナーを受講すること
- その他がん関連の講演会・研修会等を受講すること
|
| 2.がん専門薬剤師に必要な知識の修得 <5年間で修得> |
| 1)がん薬物療法に必要な一般的知識の修得 |
- 各種がんの疫学、臨床所見、診断、合併症、予後などの一般的知識
- 組織病理学的分類とステージ分類
- がんの外科的治療、放射線治療、薬物療法のそれぞれの特徴と、これらを組み合わせた集学的治療について
- 各種がんに対する代表的な薬物療法レジメンを、根治的治療、進行再発治療、術前・術後補助化学療法に分けて理解する
- 転移の過程と再発・再燃・転移後の治療法および症状マネジメントについて
- 緩和ケア、在宅ケアについて
【知識の修得が必須のがん】
【その他研修施設の状況により知識の修得が望ましいがん】
- 卵巣がん、子宮がん、泌尿器がん、頭頚部がん、皮膚がん、骨・軟部腫瘍、小児がん、肝・胆・膵がん、胚細胞腫瘍、悪性中皮腫、原発不明がん
|
| 2)がん薬物療法に関する知識の修得 |
- 各種抗がん剤について物理化学的性質・薬理作用・毒性・薬物体内動態・薬物相互作用・PK/PD・特殊集団への投与・剤形(ドラッグ・デリバリーシステムを含む)・添加物・含量規格・保険診療上の留意点などの薬学的知識
- 各種抗がん剤について薬事承認された効能効果・用法用量(保険適応の範囲)および適応条件・中止基準など使用上の注意について
- 主要ながんに対する標準治療レジメンについて、臨床的根拠となる論文、治療上の位置付け、投与スケジュール、休薬期間、投与中止基準、副作用
- 抗がん剤によって発現する副作用について、症状、グレード、好発時期、可逆性、および対処法
- 支持療法の種類、根拠、方法について
- がん性疼痛と緩和ケア
- 施設内レジメン登録制度の目的と運用について
- がん登録と施設内キャンサーボードの意義について
- 抗がん剤の臨床試験・治験に関する知識
【知識の修得が必須のがん】
【その他研修施設の状況により知識の修得が望ましいがん】
- 卵巣がん、子宮がん、泌尿器がん、頭頚部がん、皮膚がん、骨・軟部腫瘍、小児がん、肝・胆・膵がん、胚細胞腫瘍、悪性中皮腫、原発不明がん
|
| 3.がん専門薬剤師に必要な技術の修得 <必修:2年間で修得> |
- 抗がん剤の処方鑑査を適切に行えること
- 内服抗がん剤の調剤を正確に行えること
- 抗がん剤を中心とする注射薬を正確かつ安全に無菌調製するために必要な技術を有し、品質管理手順について説明できること
- 抗がん剤を希釈するために必要な溶液の選択と調製済薬剤の安定性について説明できること
- 抗がん剤の調製および投与に用いる器具・装置について説明できること
- 抗がん剤の適切な投与経路について説明できること(静脈内、動脈内、CVポート等の経路とそれらの適応)
- 静脈内投与に伴う副作用(静脈炎、過敏性反応、血管外漏出など)の発現頻度と対処法について説明できること
- 抗がん剤の廃棄手順について説明できること
- 最新の医薬品情報や臨床情報・ガイドラインを国内外のデータベースや文献情報から調査できる能力を有すること
- 臨床論文の評価法とエビデンス・レベル(EBM)の考え方を修得すること
- 患者に医薬品情報、治療スケジュール、副作用、投薬上の注意などを適切に説明できること
- 他の医療スタッフと円滑にコミュニケーションできる能力を有すること
|
| 4.がん専門薬剤師に必要な臨床経験(調剤、薬剤管理指導、緩和ケア) <2年間で研修> |
- がん薬物療法<必修:2年間で修得>
各種抗がん剤治療や支持療法について適切に提案し、チーム医療に貢献できること
- がん患者の薬剤管理指導業務
研修者は、自らが担当となって下記に示すがん患者への薬学的ケアを実践する。入院治療、外来化学療法、在宅治療のいずれの状況でも研修可とする。
消化器、呼吸器、乳房、造血器腫瘍のうち、2臓器・領域の臨床経験は必修
- 個々の患者の治療歴(とくに薬歴)を管理し、薬物治療の安全を確保するとともに、患者に対する適切な服薬指導・薬剤情報提供を実践できること
- がん薬物療法に用いられる薬剤(化学療法剤、ホルモン剤、分子標的薬剤)の特性に応じて患者の状態を適切に把握し、副作用をモニタリングできること
- 腎機能、肝機能、血液学的検査などの指標に基づいて、抗がん剤の種類、投与量、投与期間等の妥当性を評価し、必要に応じて医師に変更を進言できること
- 疼痛緩和に用いる薬剤・投与経路を患者の状況に応じて適切に選択し、副作用を管理できること
- がん又はがん化学療法に随伴する臨床症状に対して、適切な支持療法薬剤を推奨するなど薬学的管理ができること
- 医師・看護師との症例検討会に参加し、個々の患者に応じた治療方針や患者ケアについて症例経験を積むこと
- その他の臨床経験
【他に学ぶべき知識と技術の修得】<1年間で3項目を必修:3項目を選び、1項目につき4か月を目安に研修>
- がん患者の栄養管理において非経口栄養管理時の処方設計
- 麻薬の調剤と管理
- 免疫抑制剤、抗菌薬、抗がん剤等のTDMに基づく投与量あるいは投与間隔の個別最適化
- がん患者の感染対策
- がん患者の精神的ケア(サイコオンコロジー)
- 医療倫理
|
| 5.研修した成果の記録 |
- 研修した毎日の成果内容をポートフォリオで記録に残すこと。
|