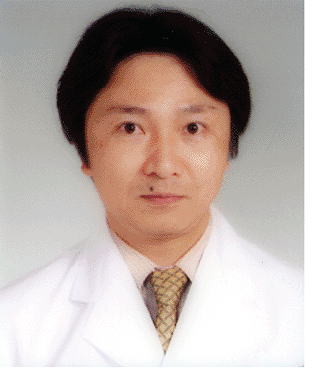
福岡大学医学部薬理学
主任教授 岩本 隆宏 ご挨拶
福岡大学医学部薬理学教室は、1974年(昭和49年)4月に初代古川達雄教授により開講され、1997年4月から二代目桂木猛教授に引き継がれました。そして、2007年4月に私 岩本隆宏が三代目の教授に就任致しました。本年、当教室は改編の節目を迎え、平均年齢40歳というフレッシュな教員体制に一新しました。教室スタッフ一丸となり、医学・医療に貢献すべく、基礎医学の教育および研究に全力を尽くす所存ですので、ご支援をよろしくお願い致します。
当教室が担当する薬理学(人体機能学Ⅳ)は、さまざまな基礎医学の知識を基盤として、また生体機能や疾病の病態生理を見据えながら、薬物治療の基礎と臨床を学ぶ総合的な学問です。臨床医学への移行期となる医学生(3年生)にとっては、“基礎知識を臨床へ有機的に結合する力”を養う重要な科目となります。そこで、人体機能学Ⅳの教育指針は、臨床医学への明確な問題意識を持って薬理学を学んで貰うために、医学教育モデル・コア・カリキュラムに出来る限り対応させています。実際の講義および実習では、医学生の学習意欲を掻き立てるために、対話型講義、図表教材重視型講義、専門家特別講義、CBT対策講義、問題解決型実習などの工夫を凝らしています。また、医学生を対象にした研究ゼミを開催し、授業枠を超えた研究コミュニケーションの場を提供しています。この研究ゼミで、科学者の“好奇心”や“感動”を少しでも学生に伝えることができればと願っています。
当教室では、“膜輸送体(トランスポーター)は創薬や疾患関連遺伝子の見地からチャネルに匹敵する重要な研究標的である”との考えから、膜輸送体を標的分子とした研究を行っています。研究アプローチは、特異的阻害薬や遺伝子改変マウスの開発が中心となりますが、当教室が得意とする薬理学的・生理学的手法を駆使して、分子レベルの視点から個体レベルにおける膜輸送体の機能・病態の解明を目指しています。現在、Na+/Ca2+交換体(NCX1)を中心とするイオン輸送体、脂質輸送体などに焦点を絞った研究を進行しています。近い将来、この分野から先駆的な治療法や診断法を開発し、臨床医学・医療の向上に貢献したいと考えています。

 May 11, 2007
May 11, 2007