診療内容
救命救急
センターFUKUOKA UNIVERCITY HOSPITAL E.C.C.M.
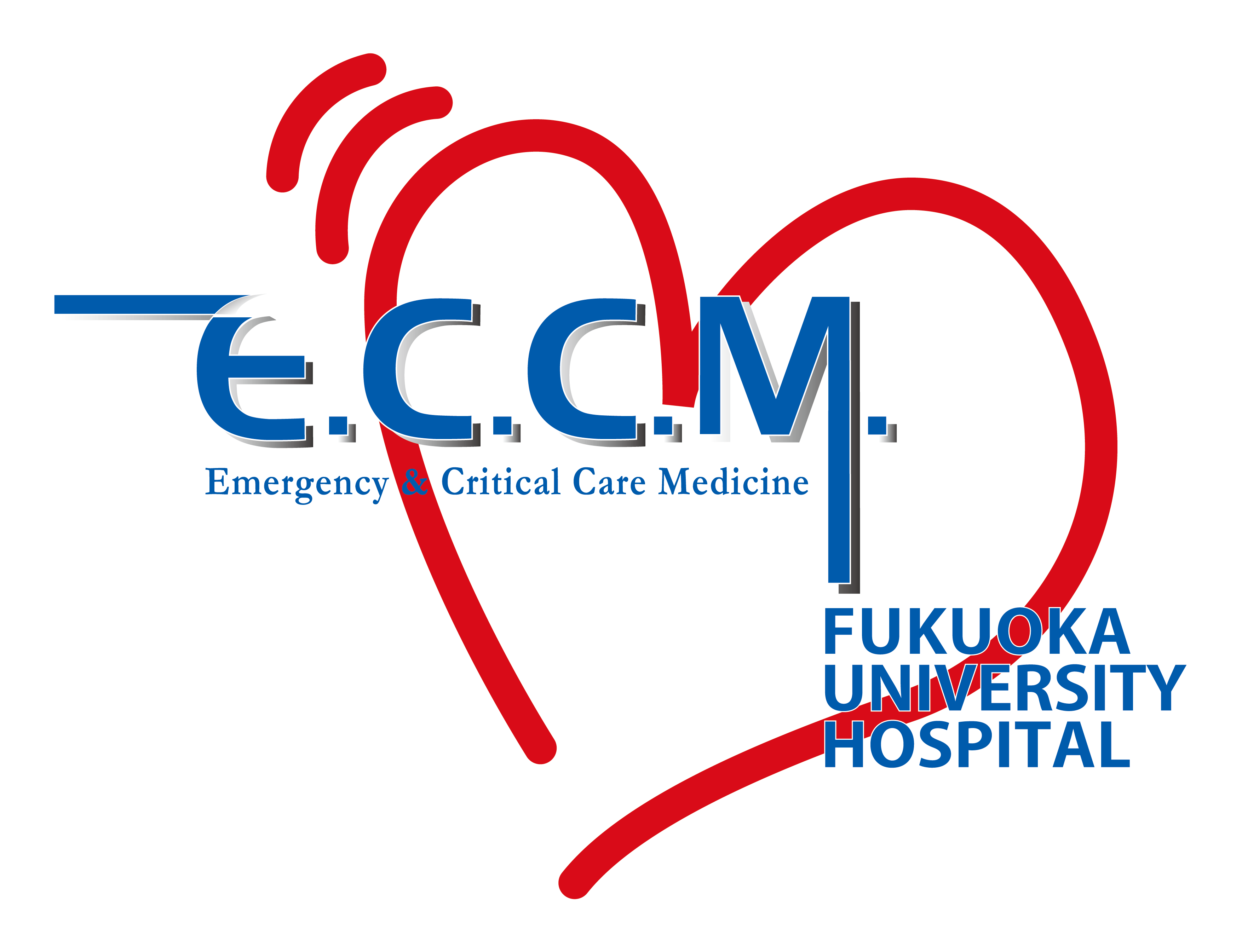
福岡大学病院 救命救急センターは、1994年に開設された大学病院併設型の三次救急医療機関です。 年間約600名の重症救急患者を、24時間365日体制で受け入れ、救命医療の最前線を担っています。
心肺停止や重症外傷、多臓器不全、脳卒中、心筋梗塞、重症感染症、薬物中毒、広範囲熱傷など、他施設では対応困難な重篤な症例にも対応しています。
また、地域全体の救急医療体制強化のため、以下の先進的な取り組みも行っています。
- 2018年: Fast Medical Response Car(FMRC)導入により、病院前救護を強化
- 2020年: 重症呼吸不全に対応するECMOセンターを設置
- 2021年: ECMO患者搬送用のECMOカー導入
- 2024年: 本館移転に伴い、EICU 12床+HCU 8床=計20床のICU体制を新設
今後とも福岡地域の救急医療に貢献できるよう努めて参ります。
センター長・副センター長
福岡大学病院 救命救急センター センター長 仲村 佳彦
福岡大学病院 救命救急センター 副センター長 喜多村 泰輔
OUR MISSION
- 私たちが使命とする、救命救急4つの柱 -
初期診療
-救急医療の最前線-
当センターは、福岡市西方地域および近隣市町村を含む約70万人の人口を診療圏として、地域の基幹医療機関や各診療科と密に連携しながら、三次救急医療を24時間体制で提供しています。
年間約500~600名の重症救急患者を受け入れ、救命に直結する初期対応を行っています。
診療体制・設備
- 初期診療室(重症対応)3室
- EICU(重症集中治療室)12床
- HCU(高度治療室)8床
計20床のICU体制で、重症患者を集中的に管理しています。個室は8床。(うち最大6床が陰圧病床に対応)
感染症を含む幅広い症例に対応可能な設計となっており、柔軟かつ安全な救急受け入れを実現しています。
初期診療の重要性
搬送されてきた患者と最初に対面するのが、この初期診療の現場です。 全身状態を迅速に評価し、診察・検査・診断・治療のすべてを時間との戦いの中で行う必要があります。
- 診断が遅れれば治療も遅れる。
- 誤診があれば命に関わる。
そんな緊張感の中でも、冷静に、迅速に、正確に対応することが求められる――それが救急医療の真髄であり、やりがいでもあります。
研修と教育:確かな手技と判断力の養成
当センターでは、初期・後期研修医を対象に、救急医療に必要な基本的手技の習得と臨床判断力の向上を重視しています。
- ACLS(高度心血管救命処置)
- JATEC(外傷初期診療)
- ICLS(心停止対応)
これらのOff the Job Training受講を推奨するだけでなく、将来的なインストラクター資格の取得も積極的に支援しています。
三次救急患者受け入れ件数
「初期診療」はまさに救命救急の最前線。
この現場での経験は、すべての臨床医にとって一生の財産になるはずです。
災害医療
福岡大学病院の災害派遣活動
当院は1996年12月27日に災害拠点病院に指定され、2003年(平成15年)より警察・消防協力の元、民間では県内最大規模の防災訓練を毎年行っています。また、2008年1月31日に福岡県災害派遣医療チーム(福岡県DMAT)に指定されました。災害が発生した際は迅速な災害医療の提供を行っています。また、海外での災害に対しても積極的に人員を派遣できるように体制を整えています。
DMAT(災害派遣医療チーム)体制
当センターでは、災害時に迅速かつ的確な医療支援を行うため、DMAT(Disaster Medical Assistance Team)を編成・運用しています。 現在の登録メンバーは以下の通りです。
- 医師:5名
- 看護師:7名
- 業務調整員:5名
地震・豪雨・大規模事故など、災害時の医療ニーズに対応するべく、定期的な訓練と研修を通じて即応力の強化を図っています。 今後も、地域・全国の災害医療に貢献できるよう、チーム体制の充実と機動力の向上に努めていきます。
| 1996年 12月 |
福岡大学病院が災害拠点病院に指定 |
|---|---|
| 2008年 1月 |
福岡県災害派遣医療チームDMAT認定および運用開始 |
| 2010年 1月 |
ハイチにおける地震被害に対する国際緊急援助隊(JDR)・医療チームへ医師派遣 |
| 2010年 8月 |
パキスタンにおける水害被害に対する国際緊急援助隊(JDR)・医療チームへ看護師派遣 |
| 2011年 2月 |
ニュージーランドにおける地震被害に対する国際緊急援助隊(JDR)・救助チーム第1陣医療班へ医師派遣 |
| 2011年 3月 |
東日本大震災へDMATチーム派遣 |
| 2016年 4月 |
熊本地震へDMAT・JMATチーム派遣 |
| 2017年 7月 |
平成29年7月九州北部豪雨(福岡)へDMATチーム派遣 |
| 2018年 9月 |
北海道胆振東部地震へDMATロジスティックチーム派遣 |
| 2019年 8月 |
令和元年8月豪雨(佐賀)へDMATロジスティックチーム派遣 |
| 2020年 7月 |
令和2年7月豪雨(熊本)へDMATチーム派遣 |
| 2023年 2月 |
トルコ共和国における地震被害に対する国際緊急援助隊(JDR)・医療チーム1次隊へ医師と看護師派遣 |
| 2023年 7月 |
令和5年梅雨前線豪雨(福岡)へDMATチーム派遣 |
| 2024年 1月 |
令和6年能登半島地震へDMATチーム派遣(3次隊) |
病院前救護
FMRC(Fast Medical Response Car)
――先制攻撃型の医療チームが、現場に駆けつける。――
2018年1月より、当センターではFMRC(エフマーク:Fast Medical Response Car)の運用を開始し、年間およそ100件の病院前救急活動を行っています。
FMRCは、救急現場に医師が迅速に出動し、その場で治療を開始することができる“欧州型ドクターカー”です。海外では「ラピッド・レスポンスカー」とも呼ばれ、近年日本国内でも注目が高まっています。
FMRCの役割と運用方法
FMRCには、医師・看護師(必要時)・運転要員が乗車し、要請を受けると救急現場や救急車との合流地点(ドッキングポイント)へ緊急出動します。
現場で救急隊と合流後、医師・看護師が救急車に同乗し、その時点から心肺蘇生や気管挿管などの高度な医療行為を開始し、病院まで患者を搬送します。
特にFMRCは、夜間やドクターヘリの着陸が難しい場所でも対応が可能で、高い機動性を誇る点が大きな強みです。
当センターは、福岡市南部地区および糸島地区のFMRCキーステーションとして、地域の救急医療を支えています。
なぜFMRCが必要か?
- 心肺停止では1分遅れるごとに生存率が7%ずつ低下
- 重症外傷では受傷後1時間以内(Golden Hour)の処置が生死を分ける
- 脳卒中・心筋梗塞といった疾患も早期治療の有無で予後が大きく変化
こうした救急疾患に対して、「病院で待つのではなく、医療を現場に届ける」というFMRCの発想は、まさに“先制攻撃型”の医療であり、救命率や社会復帰率の向上、地域医療への貢献が強く期待されています。
従来型ドクターカーとの違い
| 項目 | FMRC(エフマーク) | 従来型ドクターカー |
|---|---|---|
| 患者搬送機能 | なし(非搬送型) | あり(高規格救急車) |
| 目的 | 医師を迅速に現場へ派遣し、救急車と並行運用 | 医師が患者を搬送しながら治療 |
| 機動性 | 高い(夜間・狭所への出動可) | 限定される場合がある |
FMRCは搬送を目的とせず、あくまで医療チームがいち早く現場で治療を開始するための支援車両です。救急車との連携により、従来型以上の救命能力を発揮できると考えられています。
FMRC搭載装備(一部)
- 緊急薬剤セット
- 応急外科処置キット
- 簡易血液検査装置
- 携帯型エコー
- 心電図モニター
- 無線通信機器 など
FMRC出動件数
FMRCの導入は、病院前医療の質とスピードを一段と高める取り組みです。
地域の“最後の砦”として、これからも私たちは救急現場に全力で駆けつけます。
福岡地域MC協議会への貢献
当センターは、福岡地域メディカルコントロール(MC)協議会においても地域医療の中核としての役割を担っています。現在、委員長1名・委員1名の計2名を当センターから輩出し、救急隊の病院前活動に対する事後検証・評価を実施しています。これにより、救急現場での判断や処置の質向上、円滑な医療連携の推進に寄与しています。
病院内にとどまらず、地域全体の救急医療体制を支える一員としての責任を果たしています。
集中治療

重症患者管理
各診療科との協力体制のもとに、どのような重篤な疾患でも迅速かつ適切な集学的治療を行います。
EICU12床、HCU8床の合計20床のICUを使用し、年間500~600症例の重症患者管理を行っています。
また、8床の個室があり、最大6床の陰圧病床も保有しているので、感染症管理も対応しています。
ECMO
2020年に九州初のECMOセンターを開設以降、COVID-19 パンデミック時期には年間30症例の呼吸ECMOを管理し、全国で2番目に多い症例数を管理しました。また、全国開催される人工呼吸・ECMO 講習会の講師を派遣しています。 2021年には九州初のECMOカーを導入し、九州全域のECMO症例の集約化を行っています。
ECMOセンター

2020年7月1日開設、福岡大学病院救命救急センター併設型ECMO治療専門施設
診療チーム
全身管理チーム

――「瀕死」の状態から社会復帰へ。命を救う、その瞬間のために――
「もう助からないかもしれない」と言われた重症患者が、少しずつ回復し、社会へと戻っていく――。
その過程に寄り添い、命を救う実感を得られることこそが、救急医・集中治療医にとって最大の喜びです。
当センターの全身管理チームは、以下のような重篤な病態を対象とし、24時間365日体制で命と向き合っています。
対象疾患
- 重症呼吸不全(COVID-19 など)
- 敗血症性ショック
- 播種性血管内凝固症候群(DIC)
- 体温異常(高体温・低体温)
- 急性薬物中毒
- 心肺停止蘇生後
- 重症熱傷 など
チームの進化と先進的取り組み
この10年で全身管理チームは大きく進化を遂げました。
- 2018年:FMRC(Fast Medical Response Car)を導入し、病院前救急診療にも本格的に対応。
- 2021年7月:ECMOセンターを開設。全国でも数少ない、ECMO Car(重症呼吸器不全患者搬送専用車両)を導入し、県内外からの重症呼吸不全患者を受け入れています。
- COVID-19パンデミック下では、V-V ECMO(静脈-静脈型体外式膜型人工肺)症例数が全国第2位。九州で唯一、ELSO(国際ECMO組織)認定の教育・研究施設として、国際水準の治療・教育体制を整えています。
教育・研修について
初期・後期研修医には、以下のような実践的かつ段階的な教育を行っています。
- CV(中心静脈)ライン挿入、気管挿管などの基本的な手技指導
- 治療選択の適応判断、評価、治療方針の構築
- 専門の診療科への適切なコンサルテーション力の育成
全身管理チームの特色
救急集中治療の領域では、内科・外科の枠を越えて、急性臓器不全、多発外傷、薬物中毒、溺水、熱傷など、幅広い重症病態に対応します。 高度医療機器を用いた治療(人工呼吸、PCPS、血液浄化法など)に加え、早期からの栄養管理やリハビリテーションにも積極的に取り組み、患者さんの社会復帰を支援しています。
「命を救いたい」――その強い想いがあるなら、全身管理チームでの研修はあなたの未来に確かな力を与えてくれるはずです。
外傷チーム

――緊急度と優先度を見極め、戦略的に治療を進められる外傷医・救急医を目指して――
当センターの外傷チームでは、重症多発外傷や重症軟部組織感染症といった、複数の診療科が連携しなければ対応できない重篤な症例を数多く担当しています。これらは、まさに救命救急センターだからこそ対応できるケースです。
チーム体制
現在、外傷診療チームは救命救急科医師1名と整形外科医師6名で構成されており、初期診療から診断、緊急手術、術後管理、急性期リハビリまでを一貫して担い、シームレスな治療の提供を目指しています。
研修体制
救命救急科・整形外科それぞれの専攻医が配属された際には、科の垣根にとらわれず、「外傷診療」「整形外科的思考」「救命救急的判断力」という3つの視点から学び、緊急度・優先度を理解し、治療戦略を立てられる医師の育成を重視しています。
取り組みと実績
- ハイブリッド手術室を活用し、ナビゲーション技術を用いた低侵襲な骨盤骨折治療など、最新の治療法にも積極的に取り組んでいます。
- 重度四肢外傷や骨盤骨折に関する学会発表や臨床研究も積極的に行っており、学外での活動も活発です。
- 月1回、九州全域14施設と合同でWebケースカンファレンスを実施し、困難症例に関して多施設と意見交換を行うなど、広い視野で診療にあたっています。
外傷診療の現在
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当センターではECMOセンターを設置し、重症コロナ患者の受け入れも行ってきました。一時的に外傷患者は減少しましたが、社会活動の再開とともに再び患者数が増加し、現在ではほぼ毎日手術を行う体制が整っています。2020年度には、整形外傷手術を110例実施しました。
外傷診療の最前線で、確かな判断力と実践力を持った救急医を目指したい方にとって、ここは理想的な学びの場です。 あなたの挑戦を、私たち外傷チームが全力でサポートします。
脳外科チーム

――専門性の高い“救命救急の脳神経外科”こそ、これからの社会が必要とする診療科です――
脳血管障害や重症頭部外傷など、一瞬の判断と処置が生死を左右する脳神経疾患において、救命救急センターでの脳外科の役割は極めて重要です。私たち脳外科チームは、「命を救う脳神経外科」という専門性を追求しながら、日々最前線の医療に取り組んでいます。
対象症例
- 脳血管障害重症例(くも膜下出血、脳出血、急性期脳梗塞)
- 重症頭部外傷
チーム体制と実績
脳外科チームは、以下の多職種メンバーで構成されます。
- 脳神経外科専門医
- 脳血管内治療専門医
- 救命救急医
- 臨床研修医
年間の手術件数は約130件。内訳としては、脳動脈瘤・脳出血・脳動静脈奇形などの脳血管障害が約60例、頭部外傷も約60例と、超緊急性と重症度を兼ね備えた症例が中心です。
こうした症例に対応するため、チーム全体での連携・研鑽・教育を徹底し、「最善の医療」を常に追求しています。
教育とキャリアパス
脳外科に興味があり、自らの手で脳疾患を救命したい方、精密で高度な手術に挑戦したい方には、以下の専門資格取得を目指す道をお勧めしています。
- 日本脳神経外科学会専門医
- 日本脳血管内治療学会専門医
- 日本脳卒中学会専門医
- 日本脳神経外傷学会認定専門医
また、医師研修教育では、脳血管内治療や神経内視鏡手術などの最先端技術の習得を含め、
- 初期診療
- 周術期管理
- 専門医制度に沿った技術習得(救急科の基本領域+脳外科サブスペシャリティ)
といった、二段階制の教育体制で人材育成を行っています。
地域への貢献と“攻めの救急”
近年では、FMRCの運用も開始。
病院で待つのではなく、医師が救急現場へ向かう“攻めの救急”を実践しています。脳外科チームもFMRCに積極的に参加し、重症患者に対する早期診断・早期治療を現場で行う体制を整え、地域の皆様に迅速かつ質の高い医療を提供しています。
重症脳疾患に立ち向かう覚悟と技術を持った脳外科医を目指したい方。
ここには、あなたの志を本物にする環境があります。
福岡大学医学部 救命救急医学講座
〒814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1
TEL.(092)-801-1011(代表)